電圧レギュレータ回路の考え方
動作原理
個別素子を使用して電圧レギュレータ回路を組むことは、もうないと思いますが、三端子レギュレータの内部回路の理解の助けになる回路なので取り上げます。
一般に電圧レギュレータ回路は、図1(a)のような回路構成となります。入力電圧Vin・負荷電流Ioutに依存して出力電圧Voutが変化するのを防ぐため、オペアンプを使用した負帰還回路とします。 出力電流が大きい場合は、Q2をダーリントントランジスタにします。
VREFは基準電圧源で、入力Vin、出力電流Ioutによって変化しない定電圧源とする必要があります。 定常状態では、オペアンプのプラス側とマイナス側端子の電圧が等しくなるので(イマジナリーショート)
\begin{align} &V_{FB}= V_{REF}\\ &V_{out}=\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)V_{FB}=\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)V_{REF} \end{align}となります。
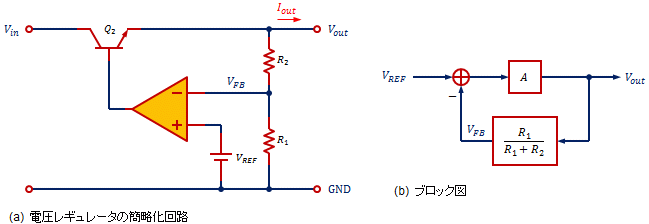
図1(b)は、信号の流れをブロック図で描いたもので、出力電圧Voutが抵抗分圧回路によってR1/(R1+R2)倍に分圧されてオペアンプのマイナス入力端子に接続され、基準電圧VREFとの差が増幅されて出力電圧がコントロールされる負帰還回路を構成しています。Aはオペアンプの電圧ゲインです。 このオペアンプは、基準電圧VREFと出力電圧を検出して得た電圧(センス電圧) VFBの差を増幅し、その差がゼロとなるように(VFB=VREFとなるように)動作点を調整するので、「誤差アンプ」とよばれます。
図1の電圧レギュレータを個別素子で組む場合、誤差アンプ、基準電圧源VREFをどのように実現するか?でいくつかの選択肢がありますが、もっとも低価格かつコンパクトに実現するには、
- 誤差アンプは、オペアンプICを使用せず、エミッタ接地アンプ1石で実現します。
- 定電圧源VREFは、基準電圧発生ICを使用せず、ツェナーダイオードで実現します。
誤差アンプをエミッタ接地アンプで実現する
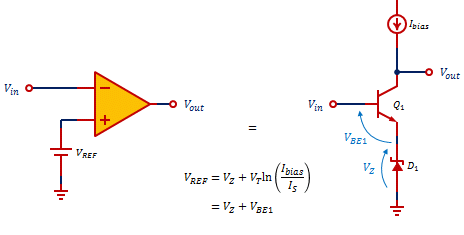
エミッタ接地アンプで誤差アンプを実現するには、図2のようにします。 図2(a)ではVin>VrefならばVout=low、Vin<VrefならばVout=highですが、図2(b)ではVin>Vz+VBE1ならばVout=low、Vin<Vz+VBE1ならばVout=highとなるので、
\begin{align} V_{REF}=V_z+V_{BE1} \end{align}となります。VREFを電源電圧に依存しない定電圧源とするため、定電流源Ibiasを使用してQ1のコレクタ電流を設定します。
ツェナーダイオードはVREFの温度係数をゼロにするために使用します。VBE1が負の温度係数(-2mV/℃)を持つので、正の温度係数をもつツェナーダイオードを選んでVBE1の温度係数をキャンセルする必要があります。ツェナーダイオードの温度係数はツェナー電圧に依存するので、結局Vz=6~7Vのものを選ぶしか選択肢はありません。
個別素子による電圧レギュレータの実用回路

図3 個別素子による電圧レギュレータの実用回路
図3は個別素子による電圧レギュレータの実用回路です。ツェナーダイオードD2でQ3のコレクタ電流(Ibias)を設定しています。ツェナーダイオードはある程度以上の電流を流さないと性能が出ないので、R3によってD1にアイドリング電流を流しています。 R3は、(Vin側ではなく)Vout側に接続しているので、入力Vinが変化してもD1を流れる電流は一定です。 C1は位相補償用(発振防止)です。
この回路に電源を投入すると、まずVinが立ち上がりD2,R5に電流が流れます。次にQ3のベース電流が流れてQ3がオン、Q3のコレクタ電流によってQ2のベース電流が流れてQ2がオン、Q2のエミッタ電流がR2を経由してQ1のベース電流となってQ1がオン、の順にトランジスタがオンし、動作を開始します。
出力電圧は
\begin{align} Vout = \left(1+\frac{R_2}{R_1}\right) V_{REF} \end{align}ですが、VREFの温度依存性を抑えるためにVz=6~7Vのツェナーダイオードを使用しなければならないので、VREF=8V弱となり、それ以上の出力電圧しかつくれません(5Vや3.3V出力はつくれません)。
このように、ツェナーダイオードを基準電圧源としたレギュレータ回路は、出力電圧の下限が8V程度なので実用的ではありません。一方、三端子レギュレータの内部回路や現代のICの基準電圧源は、バンドギャップリファレンス回路を使用しているので、出力電圧の下限が2.5Vや1.25V程度となっています。