イマジナリーショートの考え方
通常、オペアンプは、負帰還をかけて「イマジナリーショート」(仮想短絡)が成立する条件で使用します。そのようにすると、回路全体のゲインがオペアンプ内部のトランジスタ特性の影響を受けにくくなるからです。
イマジナリーショートとは、負帰還回路において入力信号と帰還信号(出力信号またはそれを分圧した信号)の差がほぼゼロとなった状態を指します。 イマジナリーショートを理解するには、負帰還回路の動作を理解する必要があるので、まず個別トランジスタによる負帰還回路、次にオペアンプを使用した負帰還回路について解説しています。
トランジスタ負帰還回路
電子回路の教科書に載っている図1のようなエミッタ接地アンプは、トランジスタ特性の個体ごとのばらつきや温度依存性によってゲインが変化するので、実用回路としては使用できません。トランジスタ特性が変化してもゲインが変化しにくくするには、負帰還を利用します。
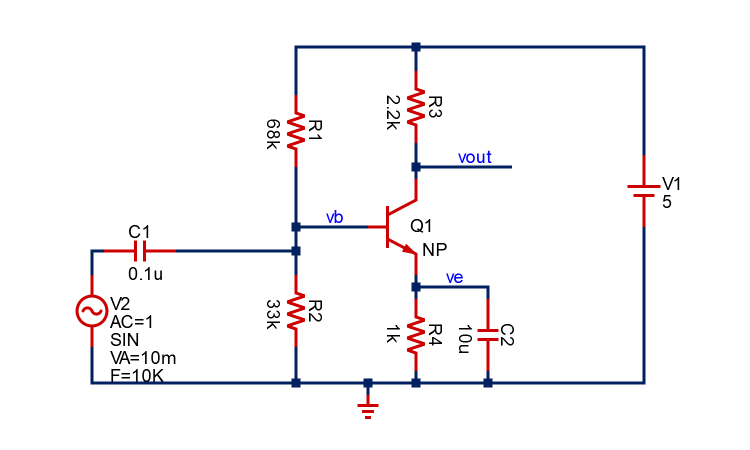
負帰還回路とは、図2のようにアンプ出力voutを帰還回路Hを介して入力に戻し、入力vinと帰還信号vfbの差を増幅するようにした回路で、基本アンプAの部分にはエミッタ接地アンプを、帰還回路Hの部分には抵抗分圧回路を使用します。ループゲイン(開ループゲイン) AHが十分に大きい場合、ゲイン(閉ループゲイン)は
\begin{align} \frac{v_{out}}{v_{in}}=\frac{A}{1+AH}\approx \frac{1}{H}\quad AH\gt\gt 1\text{ の場合} \end{align}と帰還回路の特性で決まります。つまり、基本アンプ部分の特性が多少変動してもゲインはほとんど変化しません。
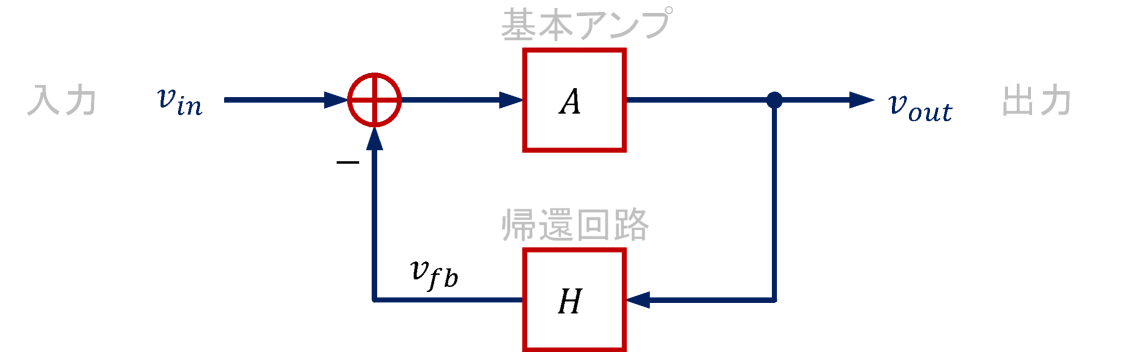
図3は2段エミッタ接地アンプに負帰還をかけた回路で、R1,R2による抵抗分圧回路が帰還回路となります(H=R1/(R1+R2))。ゲインは
\begin{align} \frac{v_{out}}{v_{in}}\approx\frac{1}{H}=1+\frac{R_2}{R_1} \end{align}となります。
図2の基本アンプをトランジスタで実現する場合、できるだけ高ゲインにする必要がありますが、1段アンプではゲインが不十分なので2段アンプとする必要があります。その結果、図3のように部品点数が多くなります。現在は、個別トランジスタを使用して図3のような回路を設計するのは現実的ではなく、オペアンプICを使用します。
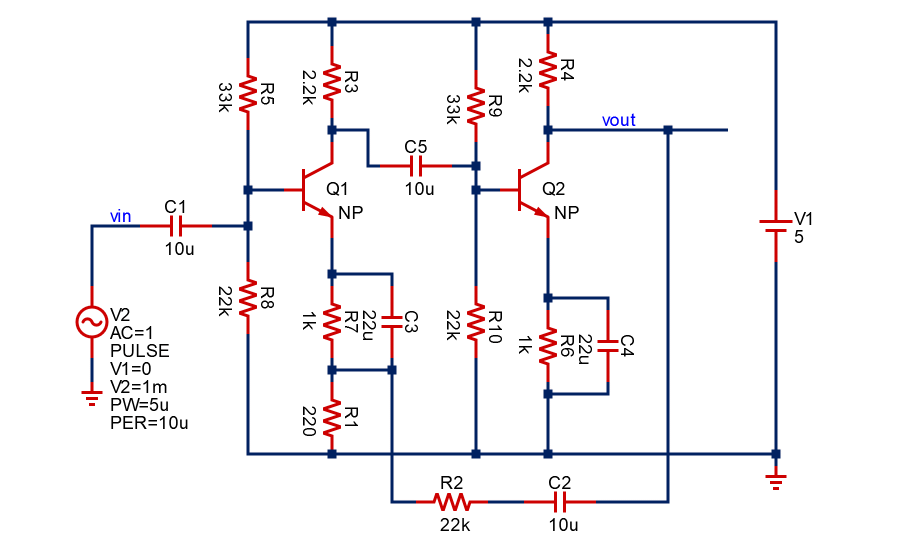
オペアンプによる負帰還回路
図2のブロック図をトランジスタで実現すると図3のように複雑な回路となりますが、オペアンプを使用すると図4(a)のように簡単になります。 オペアンプが入力から帰還信号を減じてその差の増幅をおこないます。 この回路は帰還回路のゲインH=1としたもので、Vout≈Vinとなります。
図4(a)の回路は、入力電圧Vinと出力電圧Voutを比較し、Vin>Vout (Ve>0)ならば出力Voutが増加、Vin<Vout (Ve<0)ならば出力Voutが減少するようにしています。オペアンプの+,−入力端子間に印加される電圧Veが、出力Voutによって調整されます。
\begin{align} V_{out}=AV_e = A(V_{in}-V_{out}) \end{align}オペアンプに印加される電圧Veは入力Vinと出力Voutの差なので、「誤差信号」といいます。 また、出力信号Voutは、入力に戻してオペアンプに印加しているので「帰還信号」といいます。
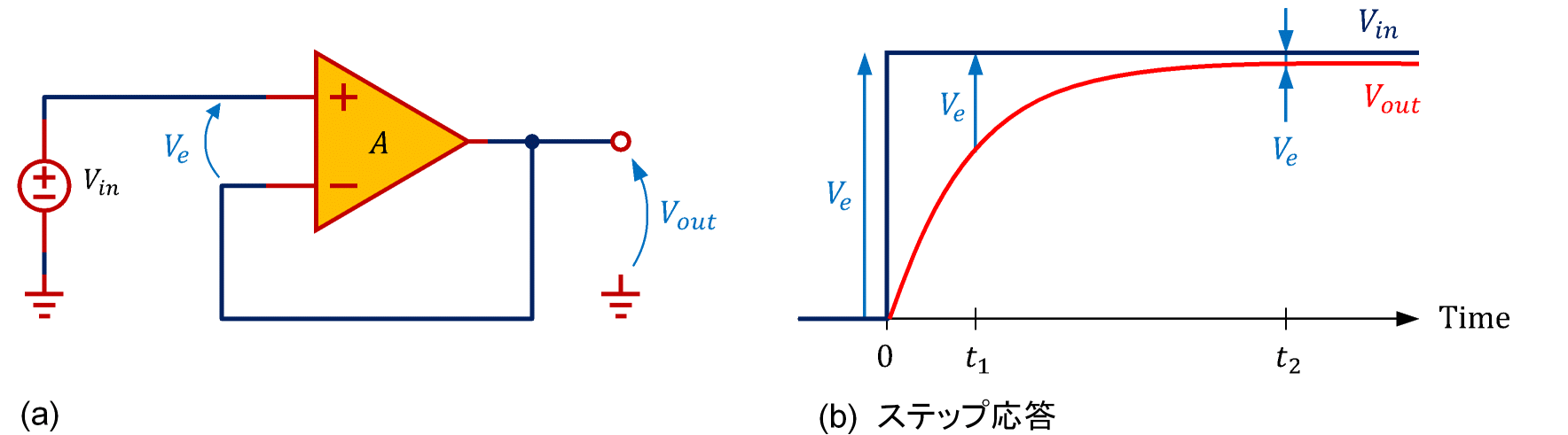
この回路のように、誤差信号を増幅して出力が調整される回路は、帰還信号(この場合は出力Vout)が入力Vinに追従して変化します(Vout≈Vinとなります)。
VoutがVinに追従する様子を直感的に理解するために、図4(b)のように時刻t=0でステップ入力を印加したときのふるまいを考えます。時刻t=0, t1, t2における回路の状態は以下のようになります。
- 時刻t=0: 誤差信号はVe=Vin-Vout=Vinとなります。このVeがA倍されて出力はAVeになろうと上昇します。ただし、オペアンプの内部回路の時定数によって変化の速度が制限されるので、(瞬時にVout=AVeとはならず) Vout<AVe の状態となります。
- 時刻t1: オペアンプ出力Voutが上昇するにつれて、誤差信号Ve=Vin-Voutは徐々に減少します。t=0の場合と同様に Vout<AVe の状態で出力Voutは上昇を続けますが、Veが減少した分だけVoutの変化の速度は小さくなります。
- 時刻t2: 誤差信号Veが小さくなると、それがA倍されても現在のVoutを維持するのが精いっぱいで、さらに上昇させることが困難になります。つまり、Vout=AVe となった状態で定常状態となります。たとえばVout=1V, A=10,000の場合、定常状態における誤差信号は Ve=Vout/A≈1/10000=0.1mV となります。
より、定常状態における誤差信号は
\begin{align} V_e=\frac{V_{out}}{A}\approx 0 \end{align}となります。オペアンプのゲインはA=10,000程度と大きいので、Ve≈0Vと近似しても問題ありません。 このように、負帰還回路では、帰還信号が入力信号に追従し、定常状態では入力信号と帰還信号があたかもショート(短絡)したかのような状態になります。この状態を「イマジナリーショート」(仮想短絡)といいます。
入力Vinと出力Voutの差(誤差信号)を増幅して出力を制御すると、出力は入力に追従してVout≈Vinとなります(オペアンプのゲインにはほとんど依存しません)。定常状態における誤差信号は、Ve=Vout/A≈0Vとなります。
ゲインを設定するには
図4の回路ではゲインが1ですが、ゲインを設定するには、図5のように出力Voutを抵抗分圧してオペアンプに帰還します。帰還信号をVfとすると、
\begin{align} V_f=\frac{R_1}{R_1+R_2}V_{out} \end{align}となります。イマジナリーショートにより帰還信号が入力信号に追従するので(Vf≈Vin )、上式に Vf=Vinを代入して
\begin{align} V_{out}=\frac{R_1+R_2}{R_1}V_f \approx\frac{R_1+R_2}{R_1}V_{in}=\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)V_{in} \end{align}となります。回路のゲインは、帰還回路の分圧比の逆数になります。オペアンプのゲインとは無関係に、外付け抵抗比R2/R1によってゲインを設定することができます。
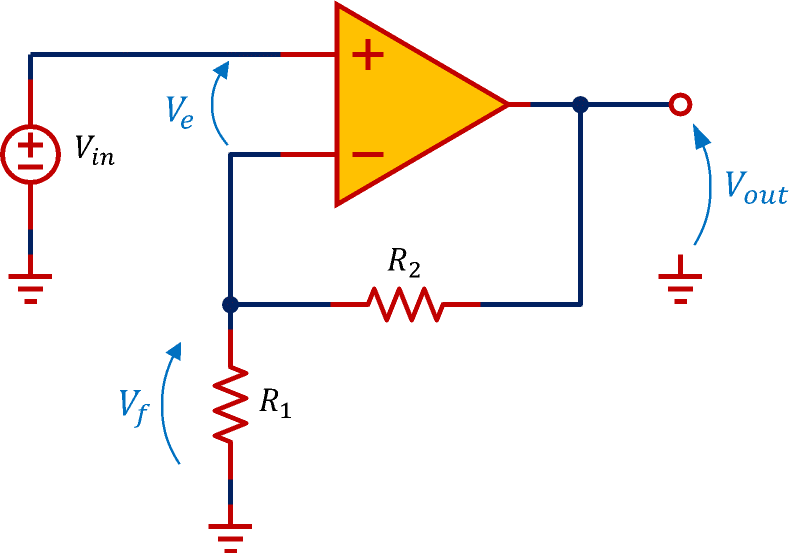
図3の回路と図5の回路の動作は同じですが、部品点数は図5のほうが圧倒的に少なく、性能もオペアンプを使用したほうが確実に良くなります。現在は、オペアンプが動作しないような高周波(無線機のアンプ)を除き、アナログ回路はオペアンプを使用して設計します。
イマジナリーショートが成立しない場合
イマジナリーショートの成立は、ループゲイン(開ループゲイン)が十分に大きいことが前提であるので、高周波領域等でループゲインが低下すると成立しなくなります。図4の回路のゲインは1ですが、オペアンプの利得帯域幅積(GBW)を超える周波数ではイマジナリーショートが成立せず、周波数の増加とともにゲインが低下します。 図5の回路についても同様に、オペアンプの利得帯域幅積によって決まるカットオフ周波数を超えるとゲインが低下します。詳しくはオペアンプ回路の周波数特性の考え方で解説しています。
また、低周波であってもオペアンプの「同相入力電圧範囲」の仕様を満足しない電圧でもイマジナリーショートが成立しません。同相入力電圧範囲を外れるとオペアンプ内部のトランジスタが能動領域を保つことができず、正常動作しなくなるからです。詳しくは4558型オペアンプの出力跳躍現象で解説しています。
正帰還回路もイマジナリーショートが成立しません。正帰還回路はコンパレータ等に利用されています。