セルフバイアス回路 (正帰還を利用したバイアス回路)の考え方
三端子レギュレータが入力電圧に関係なく一定の電圧を出力するのは、「セルフバイアス」を利用しているからです。 セルフバイアス回路とは、電源電圧を分圧して内部回路の動作点電圧をつくるのではなく、正帰還ループの中に非線形素子を組み込み、非線形素子の特性によって動作点が決まるようにした回路です(動作点は電源電圧には依存しません)。 電源回路やアナログICに限らず、最近ではマイコンにも基準電圧発生回路が内蔵されていますが、これらはすべてセルフバイアスを利用しています。
※ バンドギャップリファレンス回路もセルフバイアスを利用して出力電圧が電源電圧に依存しないようにしています。
※ 多くの電子回路の教科書で「自己バイアス回路」と呼んでいる回路は、コレクタ帰還バイアス回路で解説しています。
抵抗分圧を利用した基準電圧発生回路 (セルフバイアスではない例)
図1(a)は、セルフバイアスではない回路の例ですが、電源電圧を抵抗とツェナーダイオードで分圧して出力電圧をつくっています。負荷線を描くと図1(b)のようになり、電源電圧VCCが変化するとVout (交点のx座標)もわずかに変化します。
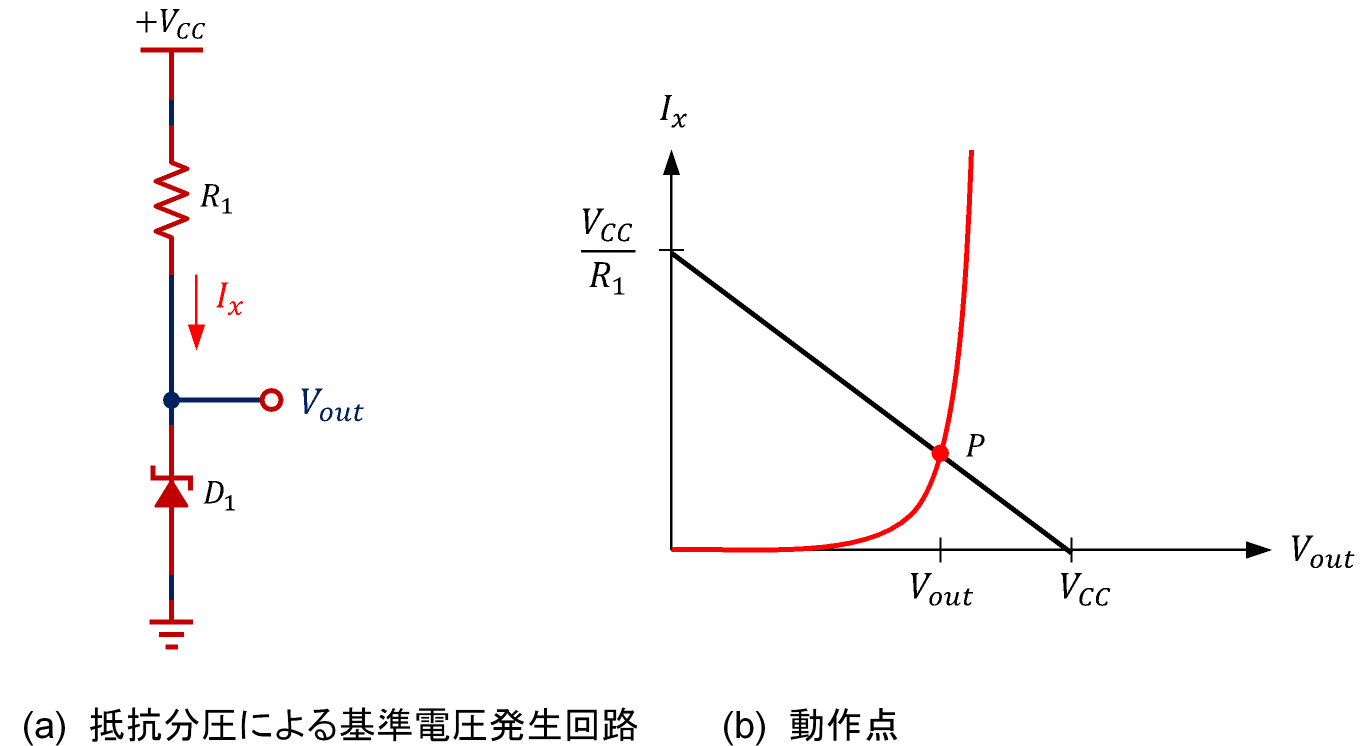
つまり、「電源電圧を分圧してつくった電圧は、電源電圧に依存して変化するので、定電圧源としては使用できない」ということがわかります。
もっとも簡単な正帰還回路(ラッチ回路)
セルフバイアス(正帰還)を利用したバイアス回路を考える前に、まず図2のような簡単な正帰還回路を考えてみます。 この回路は2個のインバータをループ接続したもので、ラッチ回路として広く利用されています。 Vin→Vout→Vxとループを一巡したときのゲインが同相で 1 以上なので正帰還回路です。
たとえばVin>Vcc/2の状態でスイッチS1を閉じると、図(b)の実線のようにVinがどんどん上昇し結局VCCに張り付きます。一方、Vin<Vcc/2の状態でスイッチを閉じた場合、図(b)の破線のようにVinはGNDに張り付きます。
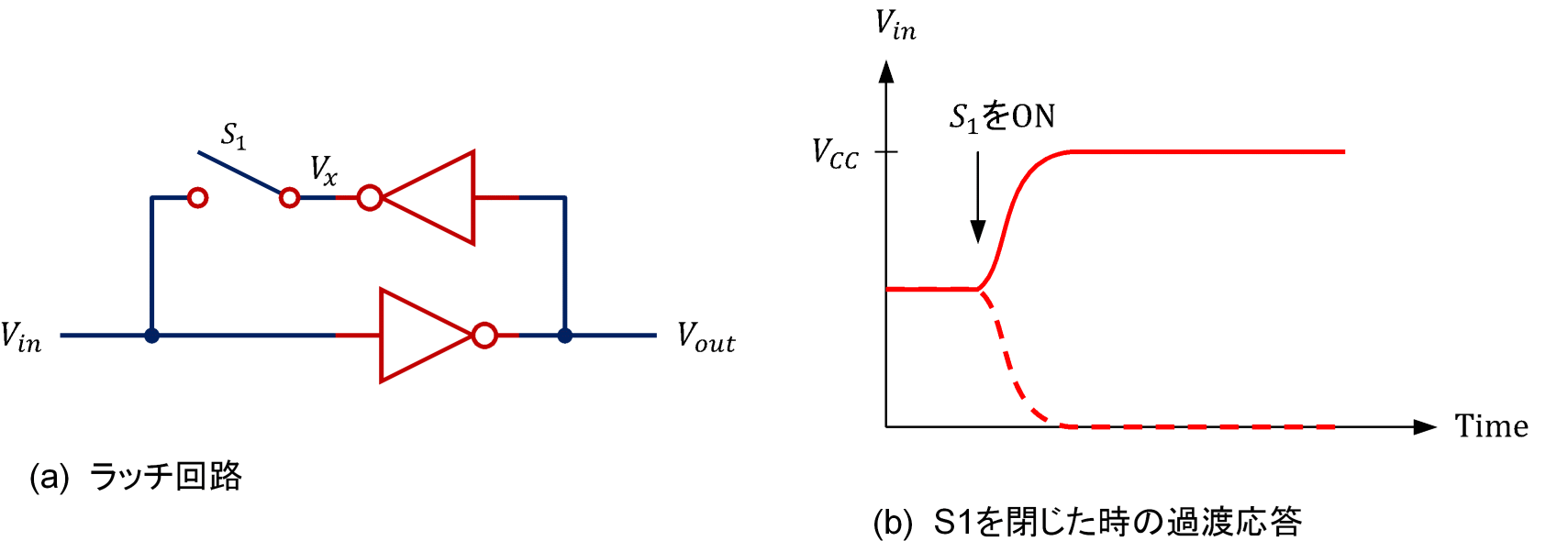
セルフバイアスを利用した基準電圧発生回路
図3(a)は図2のインバータの代わりにオペアンプを使用した正帰還回路で、動作点は電源電圧に依存しません。もしツェナーダイオードがなければループゲインが1+R2/R1>1となるので、Voutは図2と同様に0VまたはVccとなりますが、 ツェナーダイオードによってループゲインが抑えられ、ツェナーダイオードの特性によって決まる動作点に落ち着きます。
小信号ブロック図は図3(b)のようになります。rDはツェナーダイオードD1の小信号抵抗です。電源投入直後はD1がオフなのでrD≫R3、よって帰還回路のゲインH=1となります。このときのループゲイン=K>1となるのでVout, Vxが持ち上げられます。Vxがツェナー電圧を超えてD1がオンすると、rDが下がるのでループゲインも下がり、結局ループゲインが1となるような動作点に落ち着きます。 セルフバイアス回路の動作原理は発振回路と同じであることが分かります。
動作の詳細は次のようになります。図3(a)において電源投入直後Vx,Vout=0V, D1はオフと仮定します。スイッチS1を一瞬だけ閉じてVout電圧をわずかに持ち上げると、Vout→R3→Vx→オペアンプ→Voutと電圧が伝わるとともに増幅され、Vout,Vx電圧がしだいに上昇します。そして、VxがD1のオン電圧(ツェナー電圧)を超えると、D1に電流が流れて電圧の上昇が抑えられるので、結局ツェナー電圧で決まる動作点に落ち着きます。
スイッチS1部分はスタートアップ回路(始動回路)といい、電源を投入してもVout,Vx=0Vのまま何も起こらない状態を防ぐために不可欠です。S1はVoutが0V付近のときだけオンし、立ち上がったら自動的にオフするような回路とします。
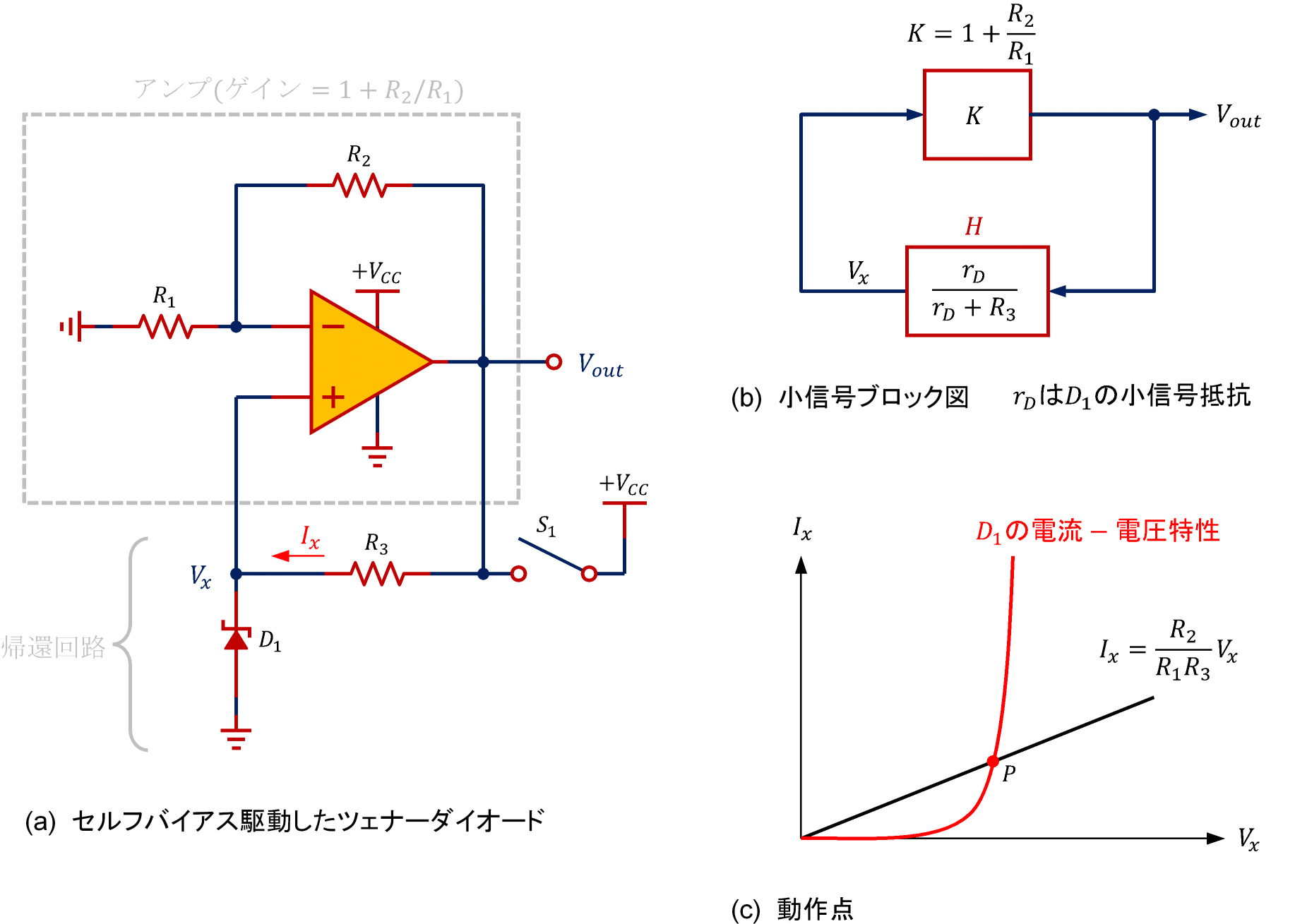
動作点は以下の手順で求めることができます。
\begin{align} \text{アンプの入出力特性:}\quad &V_{out}=\frac{R_1+R_2}{R_1}V_x\\ \text{R3の電流-電圧特性:}\quad &I_x=\frac{V_{out}-V_x}{R_3} \end{align}より、VxとIxの関係
\begin{align} I_x = \frac{R_2}{R_1R_3}V_x \end{align}が得られます。この式とD1の電流-電圧特性(赤線)の交点Pが動作点となります(図3(b))。 この動作点は、ツェナーダイオードの電流-電圧特性と抵抗値に依存しますが、電源電圧Vccには依存しないことがわかります。
このように、正帰還ループの中に非線形素子を組み込み、電圧の成長とともにループゲインが制限されるようにすると、非線形素子の特性によって決まる動作点(電源電圧には依存しない)が得られます。
※ 発振回路では、電源を投入し回路を構成するトランジスタが能動領域になると熱ノイズを種として発振が成長しますが、セルフバイアス回路ではスタートアップ回路によって回路を構成するトランジスタを強制的にオンする必要があります。スタートアップ回路がないと、電源を投入してもすべてのトランジスタがオフのまま何も起こりません。
カレントミラーを使用したセルフバイアス回路
多くの電圧レギュレータICの内部回路では、図4(a)のようなカレントミラーを使用して電流モードで正帰還をかけたセルフバイアス回路が利用されています。
図3(a)のR3,D1は分圧回路ですが、これを分流回路にしたものが図4(a)の点線部分(D1,Q1,R1)で、入力電流Iinと出力電流Ioutの関係は図4(b)の赤線のようになります。Iinが小さいうちはIinがQ1のベースに流れ、Iout=βIinとなります。Iinを増加させてR1の両端の電圧とQ1のVBEの和がツェナー電圧を超えるとD1がオンし、Iinの増分はD1側へ流れるので、Ioutはほぼ一定となります。 この分流回路にpnpカレントミラー(Q2,Q3)を接続すると、動作点はP点(Iin=Ioutとなる点)となります。電流値は
\begin{align} I_{in},I_{out}=\frac{V_Z-V_{BE1}}{R_1} \end{align}となります(VzはD1のツェナー電圧)。